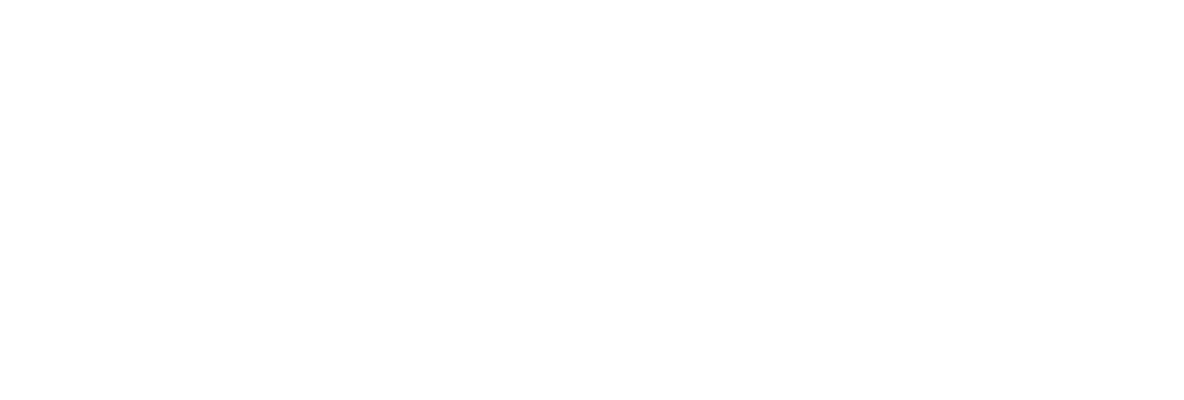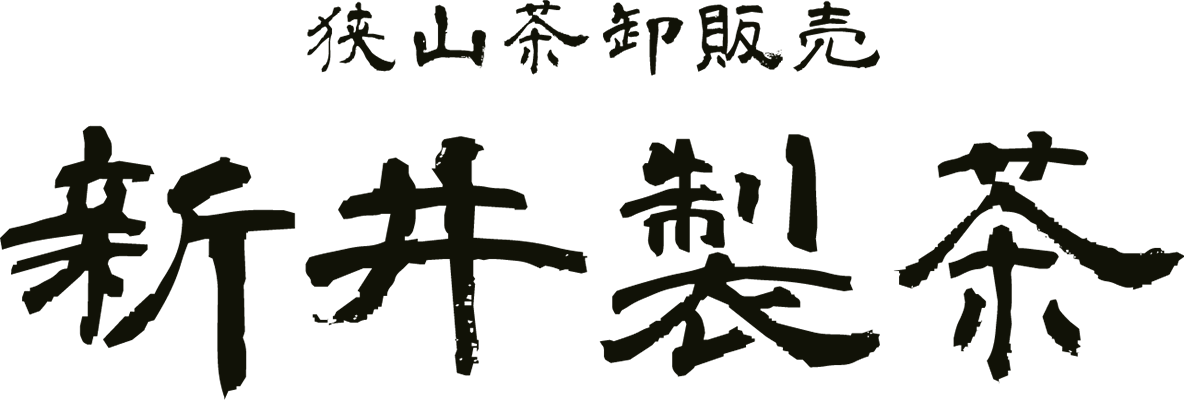【緑茶で作る玄米茶】玄米茶の作り方/玄米茶の美味しい淹れ方
更新日:2022.1.30
狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶です。
この記事では「緑茶で作る玄米茶の作り方と、玄米茶の美味しい淹れ方」を解説します。
読み終えることで、ご家庭でも簡単に美味しい玄米茶が作れます。
記事後半では、玄米茶の美味しい淹れ方も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
「玄米茶」について
まず、玄米茶についてご説明します。
玄米茶と玄米の名前が付いていますが、実際は玄米茶に玄米はほとんど使われていません。
玄米茶のほとんどが玄米ではなく、白米(精米)を使っています。
(正確には、白米を蒸した後乾燥させたものを使用しています)
玄米ではなく白米を使う理由は玄米には皮が付いており、この皮が焙煎すると焦げやすく、お湯で淹れた時に「焦げ香」や「焦げた味」として現れるからです。
一方、白米は皮がないので、焦げにくく香ばしい甘い味に仕上がります。
以上が玄米茶には玄米ではなく、白米が使われる理由です。
実際には、白米を蒸した後に乾燥させて焙煎しますが、ご家庭では白米を焙煎するだけで十分美味しく仕上がります。
この記事では白米の焙煎の様子から、合組(ブレンド)する緑茶との割合、玄米茶の美味しい淹れ方までをご紹介します。
焙煎した白米と合組(ブレンド)する緑茶
(狭山茶の深蒸し煎茶の2番茶です。目安は100g500円未満の煎茶が2番茶です)
↓↓↓

玄米茶に適したお茶は上級煎茶等よりも番茶や2番茶です。
玄米茶もほうじ茶と同様に香りを楽しむお茶です。
香りを楽しむには熱湯を使います。
なので、同じく熱湯を使って淹れる番茶や、2番茶が玄米茶には合います。
緑茶で玄米茶を作るための茶器・道具について

白米を焙煎するために、焙烙(ほうろく)・カセットコンロ(ご家庭のガスコンロでも構いません)をご用意ください。
(焙烙がない場合は鍋で代用してください)
玄米茶を淹れるのに、600ccの急須・200ccの湯呑み3客・ティースプーンをご用意ください。
白米(精米)の焙煎


まず、白米20gを焙煎します。
目安の色はきつね色よりやや進んだ明るい茶色がおすすめです。
前準備で、焙烙にある水分を飛ばすために焙烙を加熱します。
今回は火力を「中火」にしました。
焙烙が十分に温まったことを確認したら、白米20gを焙烙に投入します。
白米の色の変化を確認しながら、焙烙を動かし続けます。
動かし続けないと、白米が焦げ付くのでご注意ください。
・焙煎序盤
↓↓↓

・焙煎中盤
↓↓↓

・焙煎終盤
↓↓↓

・焙煎完了
↓↓↓

焙煎が済んだら、冷めるまで待ちます。
緑茶と玄米(焙煎済み白米)の合組(ブレンド)


焙煎済みの白米が冷めたら、2番茶と合組(ブレンド)します。
合組する比率は「1:1」にします。
どちらも20gです。
しっかりと混ぜ合わせたら完成です。

緑茶で作った玄米茶の美味しい淹れ方
ここからは玄米茶の美味しい淹れ方をご説明します。
今回は3人分の玄米茶を淹れます。
お茶の量

まず、玄米茶の計量をします。
1人3gです。
ティースプーン山盛り1杯が3gなので、3人分で3杯(9g)急須に入れます。
お湯の温度・お湯の量

玄米茶は冒頭でもお話しした通り、香りを楽しむお茶です。
香りを引き出すには熱湯を使います。
300ccの熱湯を急須に注ぎます。
急須のどの位の水位が300ccか、あらかじめ把握しておくのがおすすめです。
浸出時間(急須でお茶を置いておく時間)
浸出時間はお茶に合わせます。
今回は深蒸し煎茶なので、浸出時間は30秒です。
熱湯を注いで30秒待ちます。
廻し注ぎ

30秒経ったら、廻し注ぎでお茶の濃度と量が均等になるように注ぎ分けます。
1・2・3と注いだら、3・2・1と戻る注ぎ方です。
最後の1滴まで注ぎ切ってください。
2煎目を淹れる場合は、同じく熱湯を注いで1分程浸出させて注ぎ分けてください。
まとめ:【緑茶で作る玄米茶】玄米茶の作り方/玄米茶の美味しい淹れ方
この記事では、緑茶で作る玄米茶の作り方と、玄米茶の美味しい淹れ方をご紹介しました。
ポイントは玄米ではなく、白米を焙煎することです。
玄米を焙煎するよりも、白米を焙煎した方が香味が優ります。
焙煎済みの白米とお茶の割合は、この記事では「1:1」にしましたが、お好みで変えていただいて構いません。
【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からお知らせ
新井製茶では、旨味を引き出した狭山茶を仕上げ加工、通販をしております。
狭山茶に興味があれば【狭山茶の通販】オンラインショップをご覧ください。
新着記事
2022.11.20
2022.10.20
2022.9.14
2022.8.17
2022.7.30
2022.7.29
2022.7.28
2022.7.28
カテゴリー
- 狭山茶(3)
- 深蒸し煎茶(0)
- 手摘み茶(2)
- お茶に関すること(3)
- 急須に関すること(3)
- 狭山ほうじ茶(4)
- その他のお茶(2)
- 日本茶(緑茶)の品種(4)
- お茶の美味しい淹れ方(14)
- 水筒用のお茶(4)
- 手揉み茶(2)
- 冷茶(2)
- 和紅茶(2)
- おすすめのお茶の選び方(3)
- 玉露(1)
- 茎茶(棒茶)(1)
- 番茶(1)
- 粉茶(1)
- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)
- お茶の育て方(1)
タグ
- 100均鍋
- 1人分の淹れ方
- お湯の計量方法
- お湯の量
- お茶の保管・保存
- お茶の味の構造
- お茶の淹れ方のポイント
- お茶の美味しい淹れ方のポイント
- お茶の食べ合わせ
- パウダー茶
- ふくみどり
- ほうじ茶
- ほうじ茶の作り方
- むさしかおり
- ゆめわかば
- 冷茶
- 和紅茶
- 品種茶
- 多人数
- 多人数の淹れ方
- 大福茶
- 廻し注ぎ
- 急須
- 急須でお茶を置いておく時間
- 急須でのお茶の取り扱い
- 急須なし
- 急須の洗い方
- 急須の種類
- 急須の選びのポイント
- 急須の選び方
- 手揉み茶
- 手摘み茶
- 新茶
- 日本緑茶の種類
- 日本茶のコク
- 日本茶の淹れ方のポイント
- 時短
- 時間を計らない
- 時間短縮
- 普通蒸し煎茶
- 水筒用のお茶
- 水筒用のお茶の作り方
- 氷出し
- 浸出時間
- 深蒸し煎茶
- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較
- 深蒸し茶
- 湯冷まし
- 煎茶の2煎目以降の淹れ方
- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント
- 煎茶の選び方
- 狭山茶
- 玄米茶
- 玄米茶の作り方
- 玄米茶の淹れ方
- 玉露
- 産地茶
- 番茶
- 粉末緑茶
- 粉茶
- 茎茶