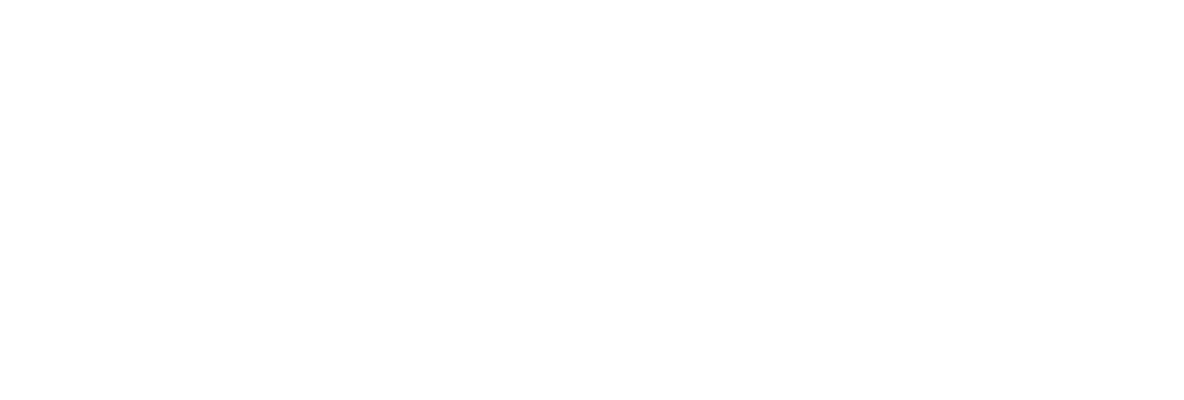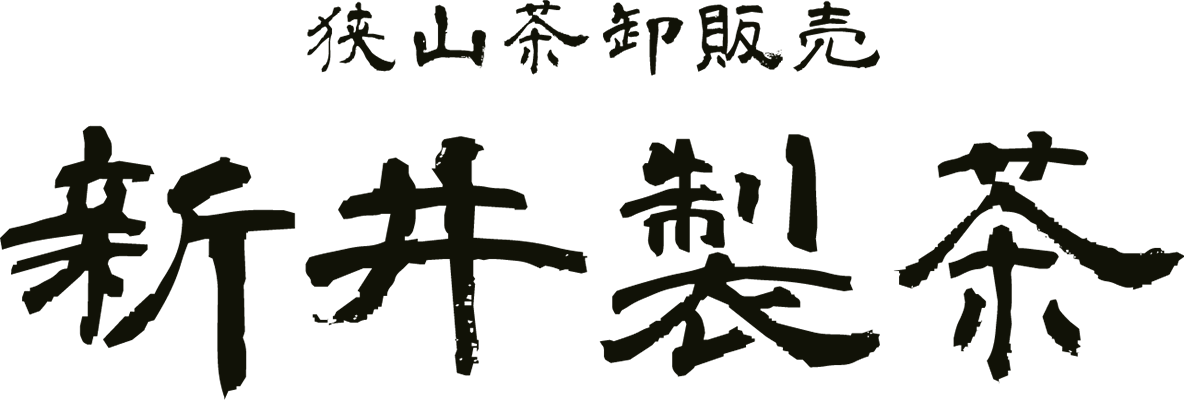【日本茶】お茶の淹れ方のコツ3選【急須なしでもお茶は淹れられます】
更新日:2022.2.11
狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶の新井です。
この記事では、私が個人的に大切と思う「お茶の淹れ方のコツ」について解説します。
普段、紹介している美味しくお茶を淹れるポイントは、お茶の量・お湯の量・お湯の温度・浸出時間の4つですが、今回は別の視点から見た日本茶を美味しく淹れるコツについて説明します。
なお、この記事で紹介するコツを押さえてお茶を淹れると、急須を使わなくても美味しくお茶を淹れることが可能です。
ですので、今回は敢えて急須を使わずにお茶を淹れたいと思います。
目次
【お茶の美味しい淹れ方・コツ1】お茶の葉を開かせる

1つ目のポイントは、お茶の葉が十分に開く器を使うということです。
これは急須にも当てはまります。
今回は、上の画像のような200ccの器を用意しました。
お茶はお湯に浸かると、葉が開くことで成分が浸出します。
逆に、お茶の葉が開きづらい状態でお湯に浸すと、お茶の成分は浸出しにくくなります。
お茶の葉が開きづらい状態とは、お茶の葉が開くスペースが狭い状態のことです。

今回は画像のような茶漉しを用意しましたが、この茶漉しの中にお茶を入れてお湯に浸すと、お茶が開くスペースが狭いのでお茶の成分は浸出しづらいです。
改善するには、200ccの器に直接お茶の葉を入れて、お湯に浸します。
こうすることでお茶の葉がお湯を吸い、しっかり葉が開きます。

今回は普通蒸し煎茶を使います。
お茶を器に入れる前に、次のポイントについてご説明します。
【お茶の美味しい淹れ方・コツ2】茶量・湯量の調整
2つ目のポイントは、お茶の量とお湯の量を調整にすることです。

お茶の量に関しては、毎回同じティースプーンを使うことをおすすめします。
ティースプーンは全て同じようには造られていないので、毎回同じものを使うと同じお茶であれば一定の量を計量でき、風味を一定にすることが可能です。
また、毎回同じティースプーンを使うことにより、風味が薄いお茶は山盛り、濃いお茶はすり切りといった調整も可能です。


お湯の量に関しては、お使いの湯呑みで湯量を調整することをおすすめします。
例えば、上の画像の100ccの湯呑みでしたら8分目が60cc、9分目が80ccということをあらかじめ確認しておきます。
あらかじめ確認しておくことで、3人分以上淹れる場合は1人60ccなので8分目、1人分の時は多めの80ccなので9分目までお湯を注げばいいので、お湯の計量が簡単です。
さらに、湯呑みでお湯の計量をすると、湯温の調整もできるというメリットもあります。

お湯の計量と湯温の調整をします。
今回は1人分のお茶を淹れます。
1人分のお茶を淹れる場合の湯量は80ccなので、100ccの湯呑みの9分目までポットの100℃の熱湯を注ぎます。

湯呑み全体が温まると、湯温は90℃程です。
湯呑み全体が温まったら、200ccの器に湯呑みのお湯を移します。
200ccの器全体が温まると、湯温は80℃程です。
煎茶の湯温の適温は70℃~80℃です。
今回は80℃で淹れます。
【お茶の美味しい淹れ方・コツ3】お茶のすくい方

3つ目のポイントは、ティースプーンでお茶をすくう時は、お茶をバランス良くすくうことです。
茶筒に保管されている人・茶袋のまま保管されている人、さまざまだと思いますが、基本的にすくい方は同じです。

形状の分かりやすい、普通蒸し煎茶で説明します。
煎茶の代表的な部位は、芽(芯)と葉です。
上の画像の左が葉、右が芽(芯)です。

上の画像の部位は葉ではなく、実は茎がお茶色に染まったものです。
柔らかい茎は、製造工程中にお茶色に染まりお茶になります。
以上のように、煎茶は芽(芯)・葉・お茶色に染まった茎で構成されています。
ティースプーンでお茶をすくう時は、芽・葉・お茶色に染まった茎をバランス良く(元々の割合で)すくうことが大切です。
バランス良くすくう意識をするだけでも良いと思います。
細かく重い芽は下の方に沈んでいるので、芽もすくえるように底の方からすくうようにしてください。
このすくい方をすることにより、飲み始めから飲み終わりまで、美味しく一定の風味で楽しむことができます。
今回は、盆にあるお茶をすくいましたが、茶筒であっても茶袋であっても「バランス良くすくう」のは同じです。

実際にお茶の計量をします。
1人分のお茶を淹れる時は、2人分のお茶の量を使うので、1人分の2g~3g×2で4g~6gのお茶の葉を使います。
先程お湯を注いだ器に、今回は直接4gのお茶の葉を入れてください。
今回のお茶は普通蒸し煎茶なので浸出時間は1分です。

1分経ったら、茶漉しで濾しながら器に注ぎます。

今回は2煎目も合わせて、コクのあるお茶に淹れたいと思います。
2煎目のお湯の量は60ccなので、湯呑みの8分目までポットの熱湯を注ぎます。
湯呑み全体が温まると、湯温は90℃程です。
2煎目は、渋味と香りを楽しむために、やや高めの90℃で淹れます。
湯呑み全体が温まったら、湯温は90℃程です。
2煎目の浸出時間は1煎目の半分の30秒です。
湯呑みのお湯を注ぎます。
30秒経ったら、1煎目と同様に茶漉しで濾しながら注ぎます。
1煎目と2煎目を合わせたお茶です。

まとめ:【日本茶】お茶の美味しい淹れ方・コツ3選【急須なしでもお茶は淹れられます】
今回は、少し違った視点からお茶の淹れ方のポイントを紹介しました。
1つ目のポイントは、お茶の葉が十分に開く器を使うことです。
急須にも同様のことが言えるので、急須を購入される時の基準にしてみてください。
2つ目のポイントは、お茶の量とお湯の量を調整することです。
毎回同じティースプーンを使うことにより、お茶の量の調整が可能になります。
また、お使いの湯呑みの何分目がどの位の湯量なのか把握することにより、湯量の調整ができます。
3つ目のポイントは、ティースプーンでお茶をすくう時は、お茶をバランス良くすくうことです。
芽・葉・お茶色に染まった茎の部分をバランス良くすくうことにより、飲み始めから飲み終わりまで、美味しく一定の味でお飲みいただけます。
【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からお知らせ
新井製茶では、旨味を引き出した狭山茶を仕上げ加工、通販をしております。
狭山茶に興味があれば【狭山茶の通販】オンラインショップをご覧ください。
新着記事
2022.11.20
2022.10.20
2022.9.14
2022.8.17
2022.7.30
2022.7.29
2022.7.28
2022.7.28
カテゴリー
- 狭山茶(3)
- 深蒸し煎茶(0)
- 手摘み茶(2)
- お茶に関すること(3)
- 急須に関すること(3)
- 狭山ほうじ茶(4)
- その他のお茶(2)
- 日本茶(緑茶)の品種(4)
- お茶の美味しい淹れ方(14)
- 水筒用のお茶(4)
- 手揉み茶(2)
- 冷茶(2)
- 和紅茶(2)
- おすすめのお茶の選び方(3)
- 玉露(1)
- 茎茶(棒茶)(1)
- 番茶(1)
- 粉茶(1)
- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)
- お茶の育て方(1)
タグ
- 100均鍋
- 1人分の淹れ方
- お湯の計量方法
- お湯の量
- お茶の保管・保存
- お茶の味の構造
- お茶の淹れ方のポイント
- お茶の美味しい淹れ方のポイント
- お茶の食べ合わせ
- パウダー茶
- ふくみどり
- ほうじ茶
- ほうじ茶の作り方
- むさしかおり
- ゆめわかば
- 冷茶
- 和紅茶
- 品種茶
- 多人数
- 多人数の淹れ方
- 大福茶
- 廻し注ぎ
- 急須
- 急須でお茶を置いておく時間
- 急須でのお茶の取り扱い
- 急須なし
- 急須の洗い方
- 急須の種類
- 急須の選びのポイント
- 急須の選び方
- 手揉み茶
- 手摘み茶
- 新茶
- 日本緑茶の種類
- 日本茶のコク
- 日本茶の淹れ方のポイント
- 時短
- 時間を計らない
- 時間短縮
- 普通蒸し煎茶
- 水筒用のお茶
- 水筒用のお茶の作り方
- 氷出し
- 浸出時間
- 深蒸し煎茶
- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較
- 深蒸し茶
- 湯冷まし
- 煎茶の2煎目以降の淹れ方
- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント
- 煎茶の選び方
- 狭山茶
- 玄米茶
- 玄米茶の作り方
- 玄米茶の淹れ方
- 玉露
- 産地茶
- 番茶
- 粉末緑茶
- 粉茶
- 茎茶