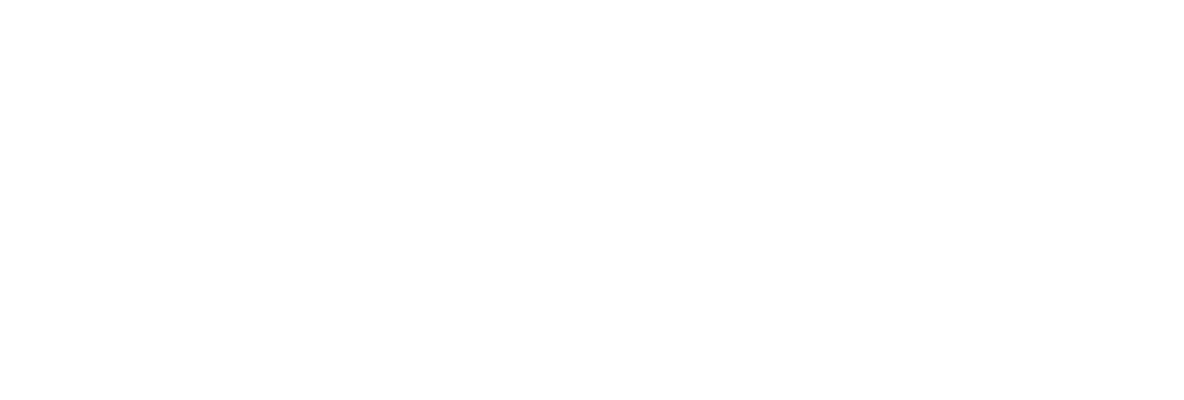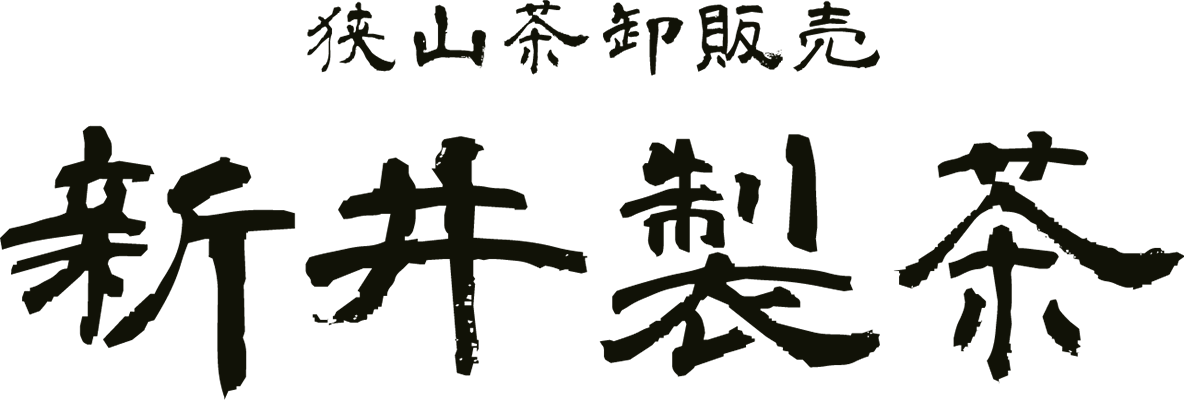お茶の2煎目・3煎目の淹れ方【ポイント3選】
更新日:2022.4.9
狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶です。
この記事では「お茶の2煎目・3煎目の淹れ方のポイント」について説明します。
湯冷ましをすることにより、1煎目では煎茶の旨味や甘味を味わえることは、多くの人が知っていると思います。
しかし、2煎目以降の淹れ方を明確に理解されている人は少ないかもしれません。
この記事では、そういった人のために煎茶の2煎目以降の淹れ方のポイントについて解説します。
煎茶の2煎目以降の淹れ方のポイントは3つあります。
1つ目は「1煎目を淹れた後に2煎目を美味しく淹れるための準備をすること」
2つ目は「湯温」
3つ目は「浸出時間」
以上、3つのポイントに注意して2煎目以降を淹れると、美味しい煎茶に淹れられます。
目次
お茶の2煎目以降の淹れ方のポイント1 「2煎目を美味しく淹れるための準備」

まず「1煎目を淹れた後の2煎目を美味しく淹れるための準備」について説明ます。
2煎目を美味しく淹れるための準備は2つです。

1つ目は「1煎目を最後の1滴まで注ぎ切る」ことです。
急須に1煎目のお湯が残っていると2煎目を淹れるまでの間に、急須の中でお茶の成分が浸出し続けます。
その結果、2煎目はとても渋いお茶になったり、苦いお茶になったりしてしまいます。
これを防ぐためには急須の中にお湯が残らないように、最後の1滴までしっかり注ぎ切ることが大切です。



2煎目を美味しく淹れるための準備の2つ目は、急須の茶漉しに張り付いたお茶の葉を剥がして急須の蓋を開けておくことです。
茶漉しに張り付いたお茶の葉を剥がすことにより、2煎目を目詰まりすることなく淹れられます。
(急須の茶漉しに張り付いたお茶の葉の剥がし方は、注ぎ終わった急須の背中を軽く叩くだけです)

急須の蓋を開けておくのは、1煎目で温まったお茶の葉の熱を逃がすためです。
お茶の葉が熱いままだと、お茶の葉は開き続け2煎目以降のお茶が渋かったり苦かったりしてしまいます。
これを防ぐために、1煎目を注ぎ終わったら急須の蓋を開けて置き、お茶の葉の熱を逃がすようにしてください。
お茶の2煎目以降の淹れ方のポイント2「湯温」

煎茶の2煎目以降を美味しく淹れるポイントの2つ目は「湯温」です。
結論から言うと、煎茶の湯温は1煎目・2煎目・3煎目と徐々に上げていくのがポイントです。

湯温を徐々に上げる理由は「煎茶の味の構造」と「湯温の違いによって浸出するお茶の成分が異なること」、この2つを考慮するからです。
煎茶の味の構造は、葉の表面が旨味・甘味、葉の中心部に近づくにつれお茶本来の渋味や苦味になっています。
そして、湯温の違いによって浸出するお茶の成分は異なります。

低温のお湯では旨味や甘味の成分、高温のお湯では渋味・苦味の成分が浸出します。
つまり、1煎目では低温のお湯で煎茶の葉の表面の旨味・甘味成分を引き出すように淹れるのがポイントです。
具体的には煎茶の場合、1煎目の湯温は70℃~80℃がおすすめです。

2煎目では、旨味・甘味成分は少なくなっているので、2煎目は煎茶の渋味を楽しむ淹れ方をします。
具体的には80℃以上の湯温で渋味成分を引き出すように淹れます。
2煎目は80℃~90℃の湯温で淹れるのがおすすめです。
ちなみに、2煎目も1煎目と同じく低温のお湯を使って淹れると、1煎目で旨味成分は浸出しているため、2煎目の風味は薄くなります。

3煎目では、2煎目よりもさらに高温のお湯を使い、煎茶の苦渋味を楽しみます。
90℃~100℃の熱湯で煎茶の苦渋味成分を引き出します。
このように煎茶の湯温は1煎目・2煎目・3煎目と、徐々に上げていくことがポイントです。
お茶の2煎目以降の淹れ方のポイント3「浸出時間」

煎茶の2煎目以降を美味しく淹れるポイントの3つ目は「浸出時間」です。
浸出時間とは、急須でお茶を置いておく時間のことです。


結論から言うと、2煎目の浸出時間は1煎目の半分程、3煎目の浸出時間は1煎目と同程度か、それよりも長くします。
2煎目の浸出時間を1煎目の半分程度とする理由は、1煎目のお湯により煎茶の葉が開き始めており1煎目よりも短時間でお茶の成分が浸出しやすくなっているからです。
なので、1煎目と同じ時間で2煎目を浸出させてしまうと渋味・苦味が強いお茶になってしまいます。
例えば、1煎目の浸出時間を1分とした場合、2煎目の浸出時間は30秒にするのがおすすめです。
3煎目の浸出時間は淹れるお茶にもよりますが、基本的には1煎目と同程度の1分か、それよりも長くします。
3煎目の浸出時間を長く取る理由としては、1煎目・2煎目で煎茶の成分の6割以上が溶け出しているためです。
長めの浸出時間をとることにより、煎茶の残りの成分を浸出させます。
まとめ:お茶の2煎目・3煎目の淹れ方【ポイント3選】
この記事では、煎茶の2煎目・3煎目の淹れ方のポイントについて説明しました。
ポイントは3つあります。
- ・2煎目を美味しく淹れるための準備をすること
- ・湯温を徐々に上げる
- ・浸出時間を徐々に短くする
1つ目のポイントの、2煎目を美味しく淹れるための準備は2つあります。
- ・1煎目を最後の1滴まで注ぎ切ること
- ・1煎目で急須の茶漉しに張り付いたお茶の葉を剥がし、急須の蓋を開けておくこと
2つ目のポイントの「湯温」に関しては、2煎目は1煎目よりも高温のお湯を使い、3煎目は2煎目よりもさらに高温のお湯を使います。
3つ目のポイントの「浸出時間」に関しては、2煎目は1煎目の半分の時間、3煎目は1煎目と同程度か、それよりも長く取ります。
【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からお知らせ
新井製茶では、旨味を引き出した狭山茶を仕上げ加工、通販をしております。
狭山茶に興味があれば【狭山茶の通販】オンラインショップをご覧ください。
新着記事
2022.11.20
2022.10.20
2022.9.14
2022.8.17
2022.7.30
2022.7.29
2022.7.28
2022.7.28
カテゴリー
- 狭山茶(3)
- 深蒸し煎茶(0)
- 手摘み茶(2)
- お茶に関すること(3)
- 急須に関すること(3)
- 狭山ほうじ茶(4)
- その他のお茶(2)
- 日本茶(緑茶)の品種(4)
- お茶の美味しい淹れ方(14)
- 水筒用のお茶(4)
- 手揉み茶(2)
- 冷茶(2)
- 和紅茶(2)
- おすすめのお茶の選び方(3)
- 玉露(1)
- 茎茶(棒茶)(1)
- 番茶(1)
- 粉茶(1)
- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)
- お茶の育て方(1)
タグ
- 100均鍋
- 1人分の淹れ方
- お湯の計量方法
- お湯の量
- お茶の保管・保存
- お茶の味の構造
- お茶の淹れ方のポイント
- お茶の美味しい淹れ方のポイント
- お茶の食べ合わせ
- パウダー茶
- ふくみどり
- ほうじ茶
- ほうじ茶の作り方
- むさしかおり
- ゆめわかば
- 冷茶
- 和紅茶
- 品種茶
- 多人数
- 多人数の淹れ方
- 大福茶
- 廻し注ぎ
- 急須
- 急須でお茶を置いておく時間
- 急須でのお茶の取り扱い
- 急須なし
- 急須の洗い方
- 急須の種類
- 急須の選びのポイント
- 急須の選び方
- 手揉み茶
- 手摘み茶
- 新茶
- 日本緑茶の種類
- 日本茶のコク
- 日本茶の淹れ方のポイント
- 時短
- 時間を計らない
- 時間短縮
- 普通蒸し煎茶
- 水筒用のお茶
- 水筒用のお茶の作り方
- 氷出し
- 浸出時間
- 深蒸し煎茶
- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較
- 深蒸し茶
- 湯冷まし
- 煎茶の2煎目以降の淹れ方
- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント
- 煎茶の選び方
- 狭山茶
- 玄米茶
- 玄米茶の作り方
- 玄米茶の淹れ方
- 玉露
- 産地茶
- 番茶
- 粉末緑茶
- 粉茶
- 茎茶