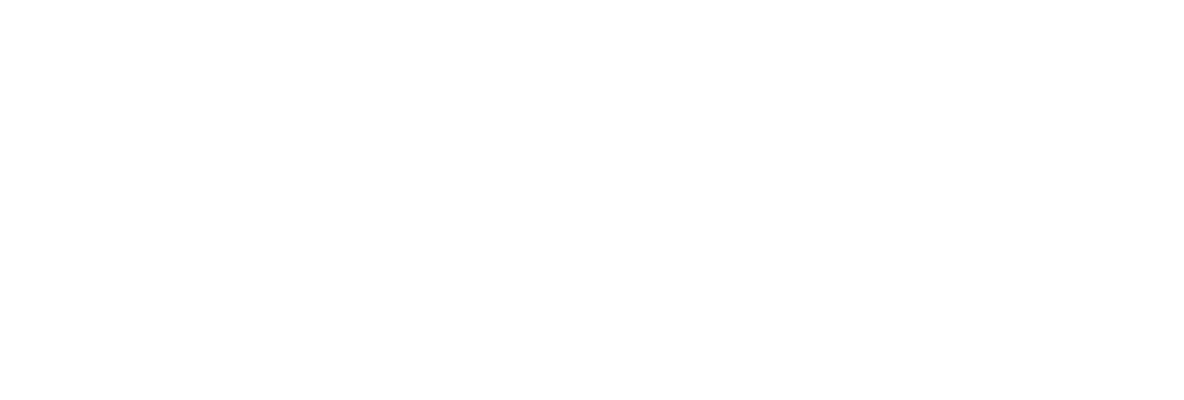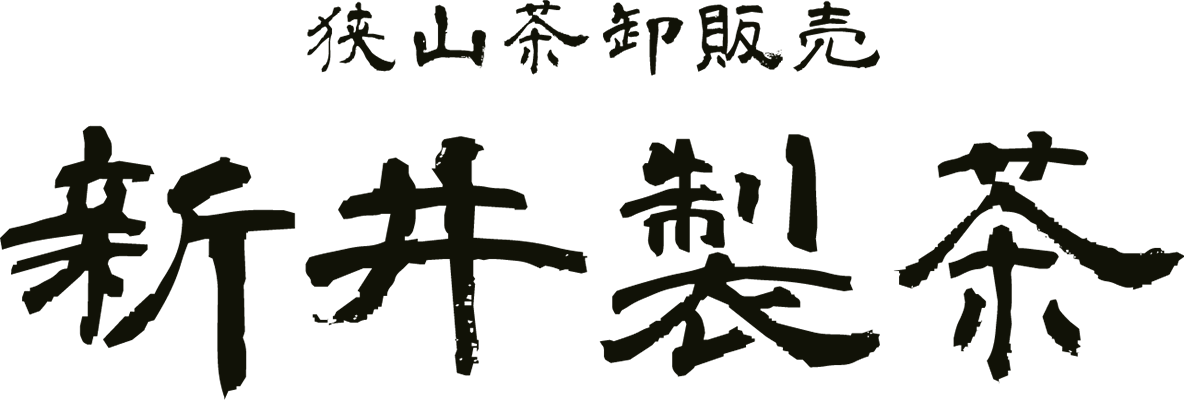【煎茶での】冷茶の作り方(品種「ほくめい」の特徴も解説)
更新日:2022.7.3
狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶です。
この記事では品種「ほくめい」を使い、煎茶での冷茶の作り方をご紹介します。
ほくめいの特性を解説し、ほくめいを使った冷茶の作り方の説明をします。
煎茶を使った冷茶の作り方のご紹介なので、品種茶にあまり興味のない方にも参考になりますよ。
目次
品種「ほくめい」について


ほくめいは母が「さやまみどり」、父が「やぶきたの実生」です。
「実生」は種で植えられたおチャのことです。
ちなみに、現在目にする茶畑のおチャは「挿し木」で植えられたものです。
挿し木とは枝を切り取り、それを植えて発根させることを言います。
ほくめいは埼玉県茶業試験場で育成されました。
摘採期は、やぶきたよりも4日程遅い晩生の品種です。

品種「ほくめい」です。
蒸し具合は深蒸しといったところです。
品種茶は、当初摘採期をずらすために導入されました。
摘採期をずらさないと、緑茶は摘んだらすぐに製造しなくてはならず、荒茶工場は連日昼夜問わず稼働しなくてはなりません。
これを防ぐために、摘採期の異なる品種茶の導入が進みました。
話を「ほくめい」に戻します。
ほくめいは葉肉が厚く、寒さ・病気に強く収量も多い、経営的視点から見ると、とても良い品種です。
品質的には、味・香りともに緑茶らしい爽やかな濃度感があります。
味に濃度があるので、それなりに渋味の強い品種です。
葉肉が厚く、味・香りに濃度があるので、深蒸し煎茶に向いた品種で、狭山茶を代表する品種と言えるでしょう。
また、萎凋させると花のような香りが発揚しやすく、渋味も抑えられる印象なので、萎凋に向いた品種とも言えます。
煎茶で冷茶を作るための茶器

煎茶で冷茶を作るのに必要な茶器などです。
250ccの急須と、100ccの湯呑みと、湯冷まし器と、300cc程のグラスと、ティースプーンを用意してください。
品種「ほくめい」を使った煎茶での冷茶の作り方
それでは実際に品種茶ほくめいの冷茶を淹れていきます。
お茶の量・お湯の量・お湯の温度・浸出時間に注目してご覧ください。
お湯の量

まず、100ccの湯呑みの9分目までポットの100℃の熱湯を注ぎます。
湯呑み全体が温まったら、急須に湯呑みのお湯を移してください。
急須全体が温まったら、急須にお茶の葉を入れるために、湯呑みに急須のお湯を移します。
お茶の量

お茶の量は、やや多めの5gがおすすめです。
ティースプーン山盛り1杯(3g)と、すり切り1杯(2g)で5gです。
浸出時間


湯呑みのお湯を急須に注ぎ、30秒待ちます。
(2煎目のために、ここで急須に入ったお湯の量を確認しておきます)
30秒経ったら湯冷まし器にお茶を注いでください。
2煎目

次に、先程確認した急須の水位まで、ポットの熱湯を注ぎます。
2煎目はすぐに湯冷まし器にお茶を注いでください。
1煎目は低温でお茶を淹れ、日本茶の旨味・甘味を引き出しました。
2煎目は熱湯でお茶を淹れ、日本茶の渋味を引き出しました。
1煎目2煎目が合わさると、日本茶のコクを味わえます。

氷を入れたグラスに、湯冷まし器のお茶を注いで完成です。
氷にお茶を当てるように注いでください。

水出しのお茶よりも、お湯で淹れたお茶を氷で急冷させる冷茶の方が、味・香りがはっきりするのでおすすめです。
まとめ:【煎茶での】冷茶の作り方(品種「ほくめい」の特徴も解説)
この記事では、埼玉県で育成された品種ほくめいと、その煎茶を使った冷茶の作り方をご紹介しました。
ほくめいは、葉肉が厚く、味・香りに濃度のある品種で狭山茶らしい品種です。
また、今回ご紹介した冷茶の作り方ですが、淹れる煎茶に合わせて浸出時間さえ変えていただければ、どんな煎茶でも美味しく淹れられます。
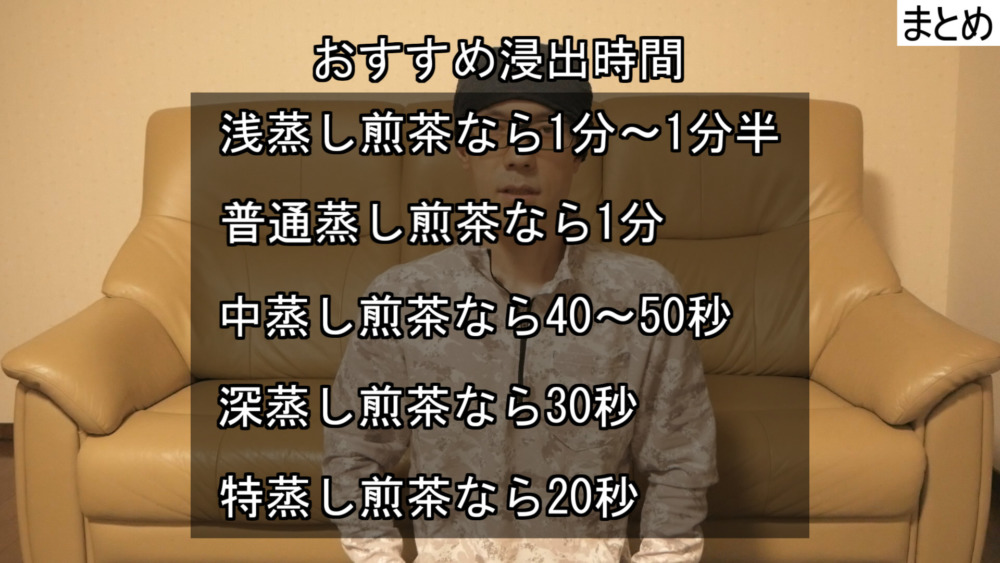
浅蒸し煎茶なら1分~1分半、普通蒸し煎茶なら1分、中蒸し煎茶なら40~50秒、深蒸し煎茶なら30秒、特蒸し煎茶なら20秒といった具合です。
【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からお知らせ
新井製茶では、旨味を引き出した狭山茶を仕上げ加工、通販をしております。
狭山茶にご興味があれば【狭山茶の通販】オンラインショップをご覧ください。
新着記事
2022.11.20
2022.10.20
2022.9.14
2022.8.17
2022.7.30
2022.7.29
2022.7.28
2022.7.28
カテゴリー
- 狭山茶(3)
- 深蒸し煎茶(0)
- 手摘み茶(2)
- お茶に関すること(3)
- 急須に関すること(3)
- 狭山ほうじ茶(4)
- その他のお茶(2)
- 日本茶(緑茶)の品種(4)
- お茶の美味しい淹れ方(14)
- 水筒用のお茶(4)
- 手揉み茶(2)
- 冷茶(2)
- 和紅茶(2)
- おすすめのお茶の選び方(3)
- 玉露(1)
- 茎茶(棒茶)(1)
- 番茶(1)
- 粉茶(1)
- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)
- お茶の育て方(1)
タグ
- 100均鍋
- 1人分の淹れ方
- お湯の計量方法
- お湯の量
- お茶の保管・保存
- お茶の味の構造
- お茶の淹れ方のポイント
- お茶の美味しい淹れ方のポイント
- お茶の食べ合わせ
- パウダー茶
- ふくみどり
- ほうじ茶
- ほうじ茶の作り方
- むさしかおり
- ゆめわかば
- 冷茶
- 和紅茶
- 品種茶
- 多人数
- 多人数の淹れ方
- 大福茶
- 廻し注ぎ
- 急須
- 急須でお茶を置いておく時間
- 急須でのお茶の取り扱い
- 急須なし
- 急須の洗い方
- 急須の種類
- 急須の選びのポイント
- 急須の選び方
- 手揉み茶
- 手摘み茶
- 新茶
- 日本緑茶の種類
- 日本茶のコク
- 日本茶の淹れ方のポイント
- 時短
- 時間を計らない
- 時間短縮
- 普通蒸し煎茶
- 水筒用のお茶
- 水筒用のお茶の作り方
- 氷出し
- 浸出時間
- 深蒸し煎茶
- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較
- 深蒸し茶
- 湯冷まし
- 煎茶の2煎目以降の淹れ方
- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント
- 煎茶の選び方
- 狭山茶
- 玄米茶
- 玄米茶の作り方
- 玄米茶の淹れ方
- 玉露
- 産地茶
- 番茶
- 粉末緑茶
- 粉茶
- 茎茶