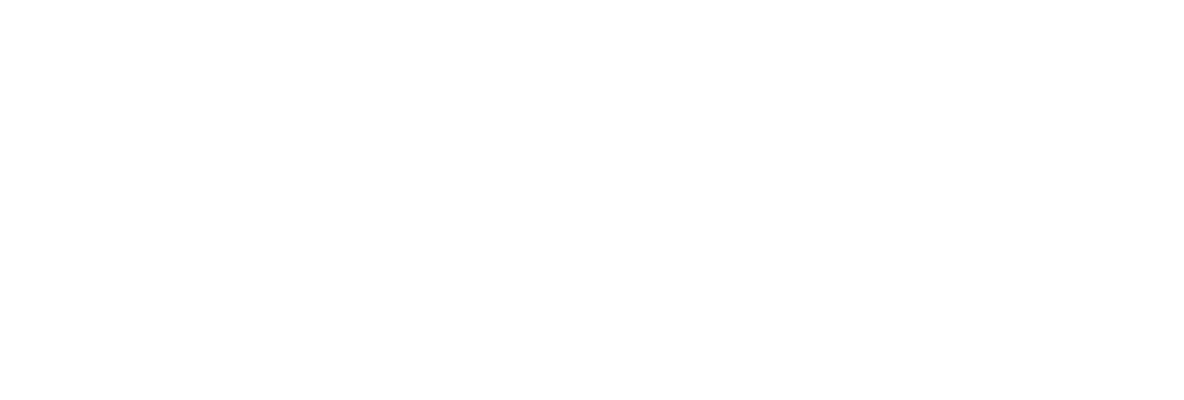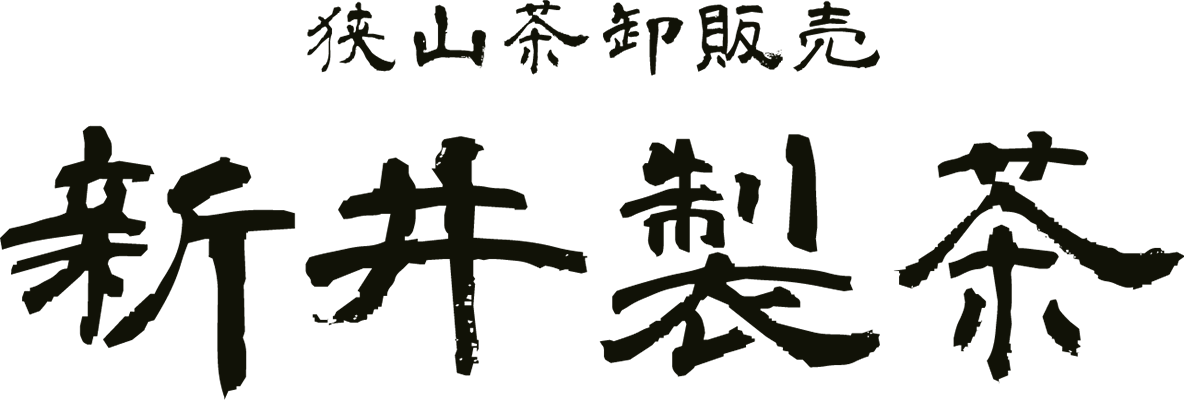【狭山茶の歴史・狭山茶の特徴とは?】おすすめの淹れ方(3人分)も解説
更新日:2021.12.2
狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶です。
この記事では、狭山茶の歴史・狭山茶の特徴・狭山茶のおすすめの淹れ方について解説します。
この記事をお読みいただきますと、狭山茶の概要を理解できます。
目次
狭山茶の歴史
狭山茶の歴史は定かではないですが西暦1,400年頃の歴史書「異性庭訓往来」には、狭山茶の起源とされる河越茶として登場しますので、西暦1,400年頃には存在していたと考えられます。
また、鎌倉時代(1,191年)に栄西というお坊さんが、宋(当時の中国)からおチャの種を持ち帰りました。
そのおチャの種が、埼玉県川越市の中院や喜多院に伝わり栽培が始まった可能性もあり、西暦1,400年以前からおチャの栽培がされていた可能性もあります。
ちなみに、中院には「狭山茶発祥之地」という石碑が建てられています。
狭山茶の特徴
狭山茶は、埼玉県西部及び東京都西多摩地域で生産されるお茶です。
茶産地としては、冷涼な地域なため、おチャの木は寒さから身を守るため葉を厚くします。
この葉肉の厚さが狭山茶の特徴になると思います。
葉肉が厚いため重量もあり、味に強い濃度感があります。

煎茶には蒸し具合で分類した、いくつかの種類があります。
たとえば、浅蒸し煎茶・普通蒸し煎茶・中蒸し煎茶・深蒸し煎茶・特蒸し煎茶です。
浅蒸し煎茶は、蒸し時間が短いためお茶の組織が崩れにくく、しっかりとした形状のお茶に造られています。
対して、特蒸し煎茶は、蒸し時間が長いためお茶の組織が崩れやすく、細かい形状のお茶に造られています。
狭山茶は全般的に深蒸し煎茶が多いと思いますが、一部の農家さんでは中蒸し煎茶や普通蒸し煎茶も造られていますね。
深蒸し煎茶が良いのか、浅蒸し煎茶が良いのかはなく、結局は好みの問題です。
私は、強火仕上げに適した深蒸し煎茶や特蒸し煎茶の荒茶を好んで仕入れますが、普通火仕上げや弱火仕上げであれば深蒸し煎茶にこだわる必要もないと思います。
話が脱線してしまいましたが、結論として狭山茶には、深蒸し煎茶や特蒸し煎茶が多く、特徴は葉肉が厚いことです。
狭山茶(深蒸し煎茶)の淹れ方
当社の狭山 深蒸し煎茶【千鳥 Chidori】を例に、狭山茶の3人分の淹れ方を紹介いたします。
下記は、10分程の動画です。
動画がお好きな方は、下記動画をご覧ください。
文章がお好きな方は、この記事をお読みください。
用意する茶器

- 急須250cc
- 湯呑み100cc
- 湯冷まし器200cc~300cc
- ティースプーン
美味しいお茶を淹れるポイント
- お茶の量
- お湯の量
- お湯の温度
- 浸出時間(急須でお茶を置いておく時間)
狭山茶(深蒸し煎茶)を美味しく淹れる手順
1.お湯の量

まず湯呑み3客にポットの100℃の熱湯を60ccずつ注ぎます。
(お使いの湯呑みのどの位が60ccか、予め把握しておくことをおすすめします)
これでお湯の計量ができました。
2.お湯の温度

煎茶の湯温の適温は70℃~80℃です。
湯温の下げ方は、器にお湯を移して、その器全体が温まれば湯温は10℃程下がります。
今回はポットの100℃の熱湯を湯呑みに移して90℃、湯呑みのお湯を急須に移して80℃です。
お茶の葉を急須に入れるために、一旦急須のお湯を湯呑みに移しておきます。
3.お茶の量

煎茶のお茶の葉の量は、1人2g~3gです。
狭山茶は味が濃厚なので2gでもOKです。
ティースプーンすり切り1杯が2gなので、3人分で3杯(6g)急須に入れます。
4.浸出時間(急須でお茶を置いておく時間)

当社の深蒸し煎茶【千鳥 Chidori】は、深蒸し煎茶なので浸出時間は30秒です。
お湯を急須に注いだら、2煎目のために水位を確認し、30秒待ちます。
(2煎目は確認した水位までお湯を注ぎます)
5.お茶の量と濃度を均等にするために「廻し注ぎ」をする

30秒経ったら、お茶の量と濃度を均等にするために、廻し注ぎで注ぎ分けし、最後の1滴まで注ぎ切ります。
急須の中にお湯を残すと、2煎目が渋味苦味の強いお茶になりますのでご注意ください。
(廻し注ぎに関しては、上記の動画をご覧いただくと分かりやすいです)

6. 2煎目の淹れ方

2煎目は狭山茶の渋味を楽しむために、1煎目より湯温を高くし90℃で淹れます。
ポットの熱湯(100℃)を湯冷まし器に、おおよそ3人分の湯量(180cc)注ぎます。
湯冷まし器全体が温まると、湯温は90℃程です。

1煎目でお茶の葉が開いていて、成分が浸出しやすくなっていますので、2煎目はすぐに注ぎ分けます。
1煎目と同様に廻し注ぎで注ぎ分けます。
なお、3煎目を淹れる場合は、ポットの熱湯を急須に注いで1分程浸出させて注ぎ分けてください。
(苦く感じる方は、お湯を注いだら直ぐに注ぎ分けてください)

まとめ:狭山茶の歴史・特徴・おすすめの淹れ方(3人分)
狭山茶の記録としては、西暦1,400年頃の歴史書「異性庭訓往来」には、狭山茶の起源とされる河越茶として登場しています。
狭山茶の特徴は、葉肉の厚さと濃厚な味わいです。
狭山茶は、おチャの木にとっては寒い地域で栽培されています。
そのため、狭山茶は寒さから身を守るために葉を厚くします。
この葉肉の厚さが狭山茶の特徴です。
葉肉の厚さは味にも現れ、狭山茶の味には強い濃度感があります。
この記事では3人分の淹れ方の解説をしましたが、下記の記事では1人分の淹れ方を詳しく解説しています。
【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からお知らせ
新井製茶では、旨味を引き出した狭山茶を仕上げ加工、通販をしております。
今回ご紹介したお茶に興味がありましたら狭山 深蒸し煎茶【千鳥 Chidori】をご覧ください。
新着記事
2022.11.20
2022.10.20
2022.9.14
2022.8.17
2022.7.30
2022.7.29
2022.7.28
2022.7.28
カテゴリー
- 狭山茶(3)
- 深蒸し煎茶(0)
- 手摘み茶(2)
- お茶に関すること(3)
- 急須に関すること(3)
- 狭山ほうじ茶(4)
- その他のお茶(2)
- 日本茶(緑茶)の品種(4)
- お茶の美味しい淹れ方(14)
- 水筒用のお茶(4)
- 手揉み茶(2)
- 冷茶(2)
- 和紅茶(2)
- おすすめのお茶の選び方(3)
- 玉露(1)
- 茎茶(棒茶)(1)
- 番茶(1)
- 粉茶(1)
- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)
- お茶の育て方(1)
タグ
- 100均鍋
- 1人分の淹れ方
- お湯の計量方法
- お湯の量
- お茶の保管・保存
- お茶の味の構造
- お茶の淹れ方のポイント
- お茶の美味しい淹れ方のポイント
- お茶の食べ合わせ
- パウダー茶
- ふくみどり
- ほうじ茶
- ほうじ茶の作り方
- むさしかおり
- ゆめわかば
- 冷茶
- 和紅茶
- 品種茶
- 多人数
- 多人数の淹れ方
- 大福茶
- 廻し注ぎ
- 急須
- 急須でお茶を置いておく時間
- 急須でのお茶の取り扱い
- 急須なし
- 急須の洗い方
- 急須の種類
- 急須の選びのポイント
- 急須の選び方
- 手揉み茶
- 手摘み茶
- 新茶
- 日本緑茶の種類
- 日本茶のコク
- 日本茶の淹れ方のポイント
- 時短
- 時間を計らない
- 時間短縮
- 普通蒸し煎茶
- 水筒用のお茶
- 水筒用のお茶の作り方
- 氷出し
- 浸出時間
- 深蒸し煎茶
- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較
- 深蒸し茶
- 湯冷まし
- 煎茶の2煎目以降の淹れ方
- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント
- 煎茶の選び方
- 狭山茶
- 玄米茶
- 玄米茶の作り方
- 玄米茶の淹れ方
- 玉露
- 産地茶
- 番茶
- 粉末緑茶
- 粉茶
- 茎茶